現在位置: 杉並区公式ホームページ > 子ども・子育て・教育 > すぎなみ子育てサイト > コンテンツ一覧(すぎなみ子育てサイト) > すぎラボ > 記事一覧 > 令和7年度 > ポイントを押さえれば苦手意識がなくなる子どものお弁当作り(2025年5月15日)
印刷
ここから本文です。
ページID : 20728
更新日 : 2025年6月1日
ポイントを押さえれば苦手意識がなくなる子どものお弁当作り(2025年5月15日)
目次

新学期が始まり、初めて子どものお弁当を作る人も多いこの時期。SNSなどにはとてもかわいらしいお弁当が並び、作る人にとってはプレッシャーが。更に小さな子どものためのお弁当なら「一人で食べられるかな」という心配。共働きのご家庭の場合は、朝から時間を掛けていられないという問題も。その結果、お弁当作りは憂鬱(ゆううつ)だと言うパパママが多いのではないでしょうか。
そこで、週に4回お弁当を持参させ、お弁当作りに慣れている幼稚園のママたちからもらったノウハウをご紹介します。
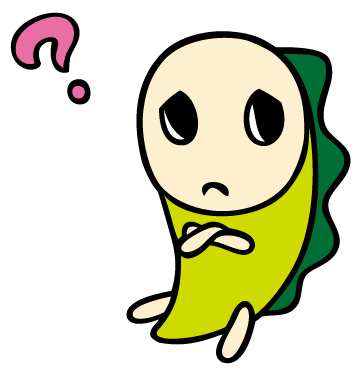
どんなお弁当を持って行くのか
食べる人によって十人十色のお弁当。今回は、初めて一人でお弁当を食べる子どものお弁当を想定してご紹介します。作り方や段取りはどんなお弁当でも共通しているので、大きな子のお弁当作りにも参考になると思います。
お弁当箱のサイズ
3歳頃の初めてのお弁当箱でおススメのサイズは、350ミリリットル程のサイズです。小さな子どものお弁当は食べきったという達成感が何よりも大切。特に初めのうちは食べやすいお弁当を心がける必要があります。
一般的に販売されている一番小さなお弁当箱は280ミリリットル程で、最初のお弁当箱としてお勧めされていますが、食べやすく盛り付けようと思うと、思っていた以上に入りません。食べやすさを考えた故に、全く量が足らなかったという事も。人一倍食べない子ども以外は、350ミリリットルのお弁当からスタートがいいです。
個人差はありますが、5歳頃になると450ミリリットル程の一回り大きなサイズを使う子どもも増えていきます。小学校からお弁当を始める場合は、最初に購入するサイズは500ミリリットル程がお勧めです。
お弁当箱は目安ですので、食べる量に応じて、デザートケースやおにぎりで調整をしてあげてください。
どんなものを入れたらいいの
繰り返しになりますが、一番に考えなくてはならない事は、わが子が食べやすいお弁当であること。SNSで「いいね」がたくさんついているお弁当、わが子は一人で食べきることができるでしょうか。初めてお弁当を食べる子どもであれば、たとえば2、3歳。かわいいキャラクターの形をしたご飯をスプーンですくって食べるのは、そう簡単ではありません。
ごはん、パン
はじめのうちは、一口か二口で食べきることができる大きさのおにぎりやサンドイッチがお勧めです。それ以上大きいサイズだと、食べているうちに崩れてしまい、食べるのが大変です。ラップでつつんで入れる方法もありますが、最初のうちはラップをはがす事が難しい子もいます。おにぎりをおかずカップに1つずつ入れてあげると、くっつきにくく取りやすいためお勧めです。
おかず
たくさんのおかずを少しずつ入れる人と3品と決めている人に分かれます。3品の場合は、お肉(お魚)、卵、野菜の組合わせがが多いです。卵の黄色と、野菜の緑や赤が入れば彩りもばっちりです。
彩りやかざり
子どもの好きなおかずは茶色いものが多めです。好きなものばかり入れてあげたら、気づけば茶色くなっていたなんてことも。子どものお弁当は見た目も大切。食べやすさを重視するなら、ピックやおかずカップでデコレーションがお勧め。あられやお魚でできたキャラクター型のチップなどで赤や黄色を入れてあげるのもいいかもしれません。

350ミリリットルサイズのお弁当。お弁当生活に少し慣れてきた頃のもので、量を増やしたお弁当です。一口サイズのごはんは最初3つからスタートしましたが、全く足らず、何とか入る5つまで増やしました。
お弁当作りでパパママの負担を減らす方法
子どもが喜んでくれるお弁当でもパパママの負担が大きいと作り続けるのは辛いです。日々お弁当に向き合っているパパママは小さな時短や工夫を積み重ねています。
作り方にマイルールを作る
日々の献立も一から考えると大変。それはお弁当も同じです。マニュアル化、ルール化して考えないでも手が動くお弁当を目指しましょう。
おかず
おかずは3種類、ご飯はおにぎりなどルールを決めるだけでも時短になります。他に月曜日はウインナー、火曜日はからあげなど、曜日で主菜のメニューを決めるのもお勧めです。
お弁当の分量
お弁当箱にいれる量もざっくり把握しておくと良いです。ご飯は何グラムと決めておくのもいいですが、例えば朝ごはんを出すお茶碗半分でおにぎりを2つ作るなど簡単に把握できると楽です。
お弁当箱の中の配置
左側におにぎり2つ、右側のこの辺りにこのおかずを入れるなど入れる場所も決めておくのも楽ができます。

冷蔵庫にそのまま入れられるおかずを常備する
冷蔵庫から出しただけ、洗うだけでそのまま入れられるおかずを常備しておくのも良いです。例えばチーズ。最初は個包装を外して、ピックを刺して入れます(冷蔵庫から出したばかりだとピックを刺すと割れてしまうので、常温に戻してから刺すと良いです)
ミニトマトは洗って入れるだけで彩りにもなります。食中毒を避けるために、しっかり水気はふき取り、ヘタも取りましょう。刺す時にお弁当箱の中で転がしがちな食材なので、ピックを刺してあげると良いです。
アスパラやスナップエンドウなど緑色の野菜は、夕食で食べる時に、まとめて茹でておくとお弁当のおかずにしやすいです。
加工品や冷凍食品にも頼る
主菜は一から作ろうと思うと大変です。前日の夕飯を取っておく、ウインナーなどの加工品を調理するなど工夫をしています。それでもお弁当は必ず手作りにすると考えているとどこかで行き詰まります。手作りがいいと思っている人でも、1つ2つ冷凍食品を常備しておくと安心です。
冷凍食品で一つ注意が必要なのは、加熱が必要かどうかと言う点。過熱が必要なものは、加熱して食べられる状態になる半調理品です。自然解凍で食べられるものとは異なりますので、くれぐれもご注意を。
まないた、包丁、火を使わない
朝、お弁当のためだけに少しだけ野菜を切るのはとても負担です。前日の夕飯の準備で、翌日のお弁当のおかずも考えて食材を切って、ラップにくるみ、保管しておきます。また、火を使うと台所から離れられないので、電子レンジやトースターを駆使するのもお勧めです。
冷ましている間を有効に活用する
食中毒を避けるためにも、ご飯もおかずもしっかりと冷ましてからお弁当箱に入れます。例えば、朝ご飯を準備するタイミングで一緒に作り、お皿の上に置いておきます。朝ご飯を食べたり、身支度を済ませている間を使って冷まして、最後にパパっと詰めるのが意外と時短になります。
なお冷ます際に、気を付けたいのが水滴。特にラップを使っておにぎりを作る場合、しっかり冷まさないとごはんとラップの間に水滴が残り、食中毒の原因に。
詰める際に別のラップに取り換えるか、ラップを外してお皿の上で冷ます方が安心です。
目標は考えないでも手が動くお弁当づくり
普段からお弁当を作っている人に聞いて気づいたのは、お弁当を考えながら作る人がいなかった事。ルールを決めて作る時に考えなくてもいいように、様々な工夫をしているのが印象的でした。仕事でもマニュアルがないと苦労します。ここでご紹介した工夫やルールを参考に、ぜひご自身のルールを作って、お弁当の負担が少しでも減りますように。
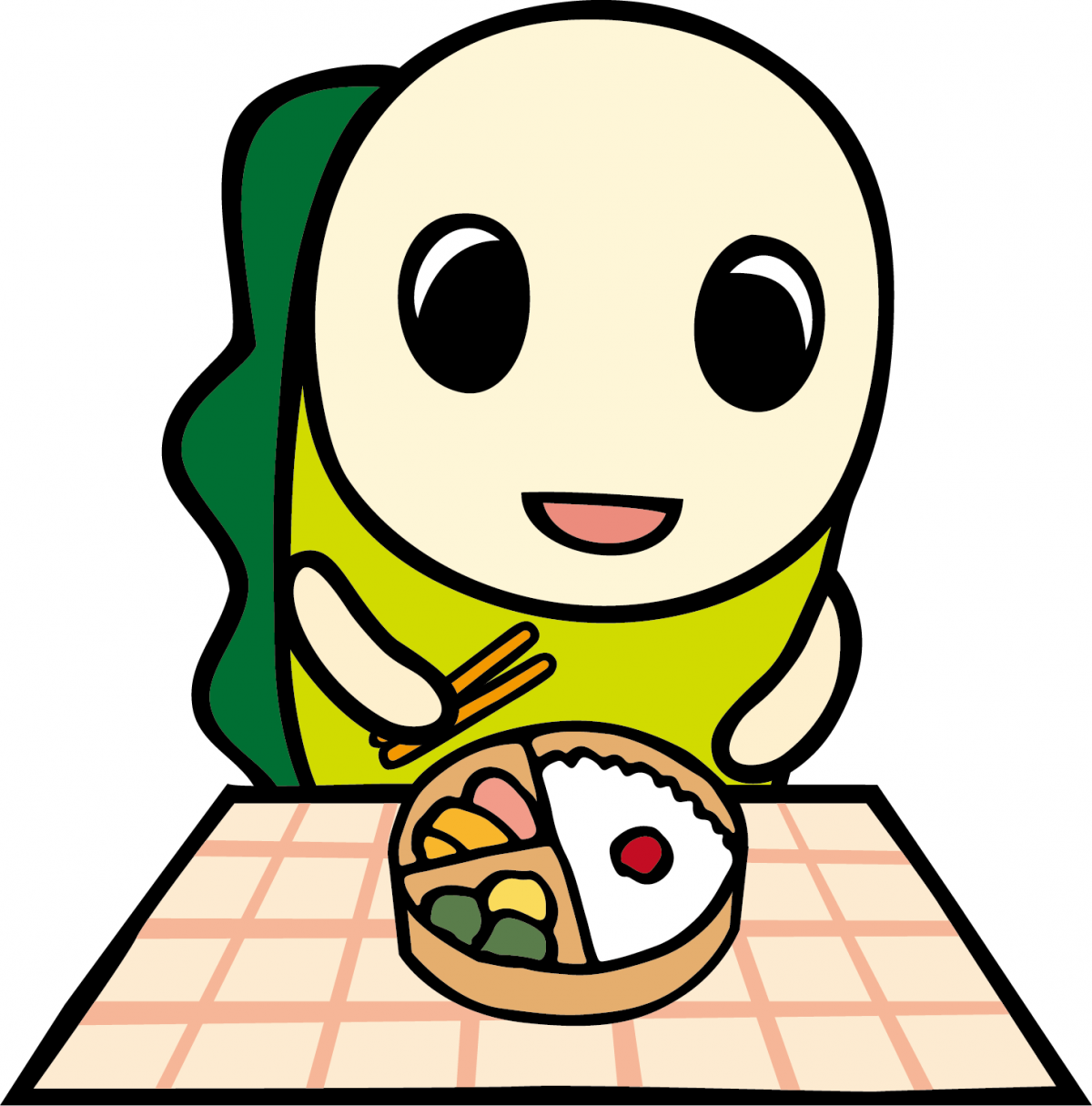
すぎラボライター らくちゃんママ
お問い合わせ先
ここまでが本文です。
同じカテゴリから探す
- 親子で楽しむ高円寺図書館(2026年1月15日)
- スイミングスクールを選ぶポイント(2026年1月15日)
- すぎはち公園へ行ってみよう(2025年12月15日)
- 家事がつらいときの味方に。産前・産後支援ヘルパーの使い方(2025年12月15日)
- 幼稚園の集まりのために公共施設を借りてみました(2025年12月1日)
- 中学生・高校生の児童館「ゆう杉並」へ未就学児を連れて遊びに行ってきました(2025年12月1日)
- ベビーシッター制度を活用して無理のない育児を(2025年11月1日)
- すぎなみフェスタ2025に行ってみませんか?(2025年10月31日)
- 年の差兄弟でも楽しめる高井戸地域区民センター(2025年10月1日)
- ペットボトルでゼリー作り(2025年9月15日)
- 親子でアニメの世界へ!「杉並アニメーションミュージアム」に行ってみた!(2025年9月1日)
- 長い夏休みのお昼ごはんは工夫して乗り切ろう(2025年8月1日)
- 一本松公園へ行ってみよう(2025年7月15日)
- 令和7年 杉並区の水遊び場情報(2025年7月1日、8月20日更新)
- パパが工夫している子育て 家庭も仕事も大切に(2025年6月15日)
- 手作りおもちゃ・紙で作るドーナツ(2025年6月15日)
- 子育てびっくり体験談をまとめてみました(2025年6月1日)
- ポイントを押さえれば苦手意識がなくなる子どものお弁当作り(2025年5月15日)
- 柏の宮公園へ行ってみよう(2025年5月1日)
- 梅里中央公園へ行ってみよう(2025年4月15日)
- わが子が小学校に入学する時に知っておくと良いパパママの心づもり(2025年4月1日)
- わが子が幼稚園に入園する時に知っておくと良いパパママの心づもり(2025年4月1日)